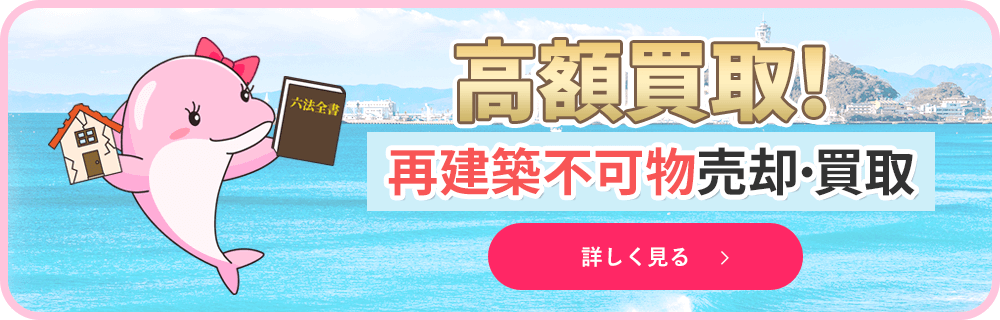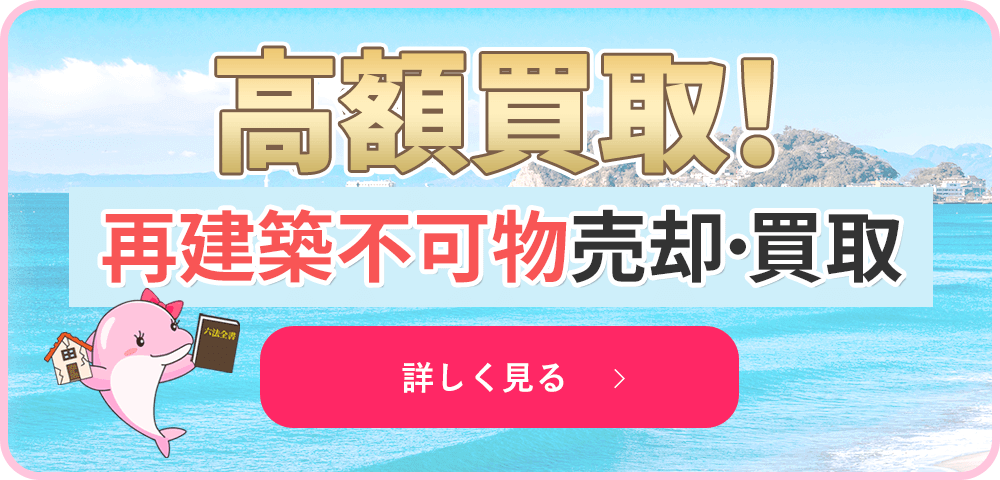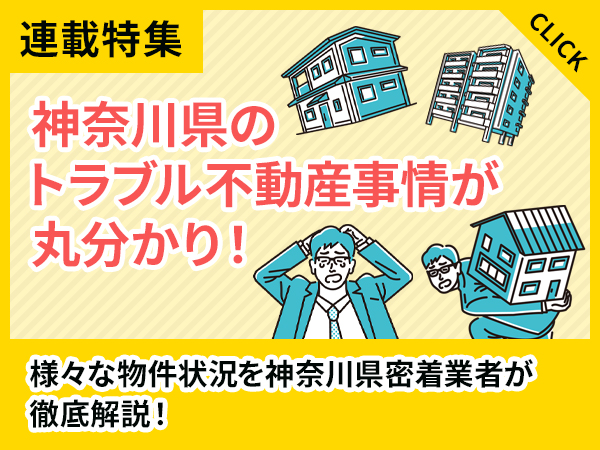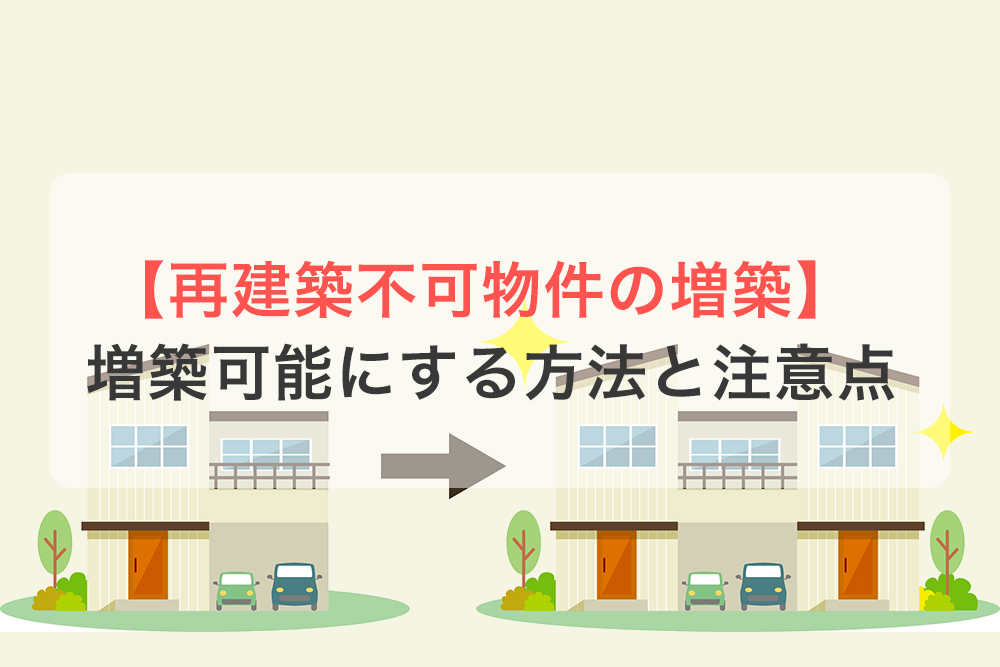
2022年08月14日
建物を新たに建てることが認められていない再建築不可物件ですが、増築の場合はどうなのでしょうか?新築はダメでも従来の建物に手を加えたり追加したりする増築ならなんとなく認められるような気もします。
今回は再建築不可物件の増築に関する注意点や抑えておくべきポイントについてご説明します。
目次
再建築不可物件は増築できない?
結論から言うと再建築不可物件は増築に関しても認められていません。そもそも建築は建築基準法に則って行わなければならず、建物を建てる際には建築許可申請を行わなければなりません。新築はもちろん、増築や建物の構造などを大きく変更する大規模修繕など改築を行う際にも建築許可を申請する必要があります。
再建築不可物件とは建築基準法第43条で定められている幅員4m(一部地域では6m)以上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務を満たしていないがために建築許可が下りない物件のことを指します。
ちなみに建築許可申請が不要な範囲でのリフォームや修繕であれば可能です。
【豆知識】リフォームと増築の違い
増築工事とは延床面積を増やすための工事のことを指します。たとえば敷地内に新たに建物を建てたり今の建物の隣に部屋を追加したり2階建てを3階建てにしたりといった工事が該当します。
リフォームは延床面積や建物の構造、間取りを変えずに部分的に変更することです。たとえば壁紙や床材を張り替える、キッチンや浴槽などの住宅設備を交換する、外壁を塗り替える、屋根や雨といを修理するといった作業があてはまります。こうした比較的小規模な工事であれば建築許可申請は要りません。逆に言えば再建築不可物件においては小規模なリフォームや改修をするくらいしか手立てがないとも言えます。
再建築不可物件の増築を可能にするための方法

とはいえ、諦めるのはまだ早いです。再建築不可物件で増築がまったくできないかといえばそういうわけでもありません。もう一度おさらいすると、再建築不可物件は接道義務を満たしていないが故に建築許可が下りない物件のことを指します。つまり、建築基準法の要件をクリアして建築許可が下りるようにすれば増築は可能になるということです。
「セットバックを利用する」「隣接している土地を購入する」のいずれかの方法で接道義務を満たせば、増築ができるようになります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
セットバックの利用
セットバックとは「後退」という意味です。接している道路の幅員が足りない場合、自分の土地を後退させてその分を道路としてみなしてもらうことで、接道義務を満たすことができます。
たとえば敷地が幅員3.8mの道路に接しているとしましょう。このままでは「幅員4m」という要件を満たせないため、建築許可は下りません。そこで、セットバックして20cm分を行政に明け渡して道路にしてしまえば、接道義務を満たすことができて増築できるようになります。
また、向かいにも家がある場合は自分が10cm、お向かいさんが10cmセットバックするという方法でも接道義務を満たすことができます。
再建築不可物件を建築可能にするためによく行われる方法です。費用をかけずに行える反面、セットバックした分だけ敷地が狭くなってしまうというデメリットもあります。また、多くの場合行政に土地を寄付するという形で明け渡すことになるため、対価はもらえません。
隣接している土地の購入
隣の敷地が道路に接している場合は、隣地を購入して自分の土地にしてしまうことで接道義務を満たすことができます。自分の土地がまったく道路に接していない場合は隣地をまるまる買わなければならないかもしれませんが、一部のみ接しているケースでは限られた土地を購入すれば済む場合もあります。
たとえば道路に接している間口が1.9mの場合、隣人から10cm分だけ土地を譲ってもらい、それを間口にすることで、接道義務を満たすことが可能です。
この方法であれば自分の土地が狭くなってしまうことはありません。ただし、土地を購入するためには費用がかかり、隣人と交渉する必要があります。中には土地を譲ってくれなかったり、足元を見て高額な対価を請求してきたりする地主もいます。どうしても物件を増築して住みたい、事業に必要といった事情がない限り、現実的な策とは言えません。
増築する際に注意するポイント5つ
- 建築基準法上の規定範囲内で増築
- 耐震性の問題
- 雨漏りの問題
- 固定資産税の増加
- 建て替えの検討
増築に関する注意点は数多くありますが、特に建築基準法の規定範囲内であるか?耐震性がしっかり確保できているか?雨漏りがしていないか?を検討しましょう。また、固定資産税などのランニングコストにも注意が必要です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
建築基準法上の規定範囲内での増築

セットバックや隣地の購入で接道義務をクリアしたとしても、他にも建築基準法では増築に関するさまざまな規制が敷かれており、それらをすべて満たさなければなりません。前提として10㎡を超える増築は建築許可申請を行う必要があります。それに加えて各要件に合致させて増築部を設計しなければなりません。
たとえば敷地に対して建築が可能な建物の床面積の割合のことを建ぺい率といいます。土地ごとに上限の建ぺい率は決められています。たとえば建ぺい率が70%と決まっていて60㎡の敷地で増築する場合は40㎡が限度となります。
敷地面積に対する延床面積の割合である容積率も重要です。やはりこれも土地ごとに上限が決められています。たとえば容積率が200%で60㎡の敷地で2階建ての増築をする場合は、1階と2階の床面積の合計で120㎡までに抑える必要があります。
耐震性の問題

日本は地震大国であり、震災への備えも欠かせません。特に再建築不可物件はいわゆる旧耐震基準(1981年5月31日までに適用されていた耐震基準)で建てられているケースがほとんどです。それ以降の新耐震基準は「震度6強、7程度の地震でも倒壊しない水準」となっていますが、旧耐震基準は「震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準」とされていて、今よりも基準が甘いです。加えて劣化していて建物の強度も弱くなっているリスクがあります。
増築を行う前に、そもそも物件全体の耐震補強をしなければいけないケースも多いです。その場合は柱の間にフレースや耐震壁を入れるような大規模な工事が必要となり、費用もかかりますが、かけがえのない命と大切な財産を守るためには必要不可欠なことです。
増築した場合は従来の建物の耐震性と新しい建物の耐震性に差が生じます。耐震性が異なる建物が1つになるとバランスが悪くなって倒壊するリスクがあるので要注意です。
雨漏りの問題
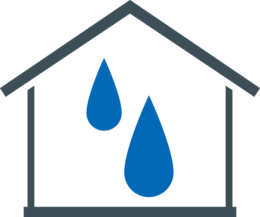
雨漏りの放置も相当危険です。雨水が建物内部に侵入することで柱や梁などの構造体が腐食してしまいます。そのまま放置しておくとシロアリ被害に遭ったり地震の際に倒壊したりするおそれもあります。特に築年数が古い再建築不可物件の場合は屋根の防水シートが劣化していて雨漏りしている可能性が高いです。
雨の日に天井にシミができたり雨水が垂れてきたりしている場合はかなり進行しており、大規模な修繕が必要になるケースが多いです。また、そうでなくても天井裏に雨水が侵入していることがあります。雨漏りをしている際には、まずはその修理からはじめましょう。
また、古い建物と増築した建物の接合部は隙間が発生して雨漏りしやすい傾向があります。こちらもしっかりと対策をしましょう。
固定資産税の増加

固定資産税あるいは都市計画税は物件の評価額によって決まります。一般的に再建築不可物件は資産価値が低いとみなされるため、これらの税金の額も安い傾向にあります。しかし、セットバックや隣地の購入によって通常物件になった場合は評価額が上がって固定資産税や都市計画税が高くなる可能性があります。また延床面積が増えることでも税額が高くなってしまうので要注意です。
特に今でも固定資産税や都市計画税が負担と思われている方は、増築することでさらに負担が重くのしかかることになるので、事前にしっかりと検討しておきましょう。
建て替えの検討
以上のように再建築不可物件を増築する際にはさまざまな問題が発生する可能性があります。たとえば増築をして古い建物の耐震補強工事や雨漏り修理工事などを行うとなるとかなり高額になってしまいます。また、毎年支払う税金も高くなるでしょう。
しかも現存する建物はリフォームや修繕をしたからといって新しくなったり、大幅に性能がアップしたりするわけではありません。増築をすればどうしても建物全体がアンバランスになりがちです。
いろいろお金を使って無理に増築するよりは、一層のこと現存する建物を解体して新しく建物を建ててしまったほうが、コストも時間もかからない可能性があります。
よほどの事情やこだわりがなければ、建て替えという選択肢も検討されることをおすすめします。再建築不可物件の建て替えについては「【再建築不可物件】建て替えする裏技を大公開!」で詳しく紹介しています。
売却して買い替えする選択も

増築ではなく建て替えを検討することで、耐震補強や修繕などのコストを抑えることができます。しかし、再建築不可物件においては建て替えも通常の物件と比較するとハードルが高いです。建物を解体して新築するにしてもやはり接道義務を満たすためにセットバックや隣地の購入をしなければならず、損をする可能性があります。そもそも、建て替えができないから増築でなんとかしたいと思っている、建て替えができれば最初から増築など検討していないという方も多いかと思います。
そこで再建築不可物件の活用に本当に困られているのであれば、売却してしまうのも一つの手段です。とはいえ一般的な不動産会社では資産価値が低いため相手にされなかったり二束三文で買い叩かれたりする可能性があります。
契約不適合責任が生じるのも大きなリスクです。契約不適合責任とは契約の内容と現物が異なっている場合に売主が買主に対して負わなければならない責任のことを指します。仮に瑕疵(不具合)があった場合、損害賠償請求や減額請求、追完請求(修理費など)、契約解除請求などがなされる可能性が高いです。特に再建築不可物件ではこうしたトラブルが発生しやすくなります。
再建築不可物件をスムーズに売却するために
餅は餅屋ということわざがありますが、再建築不可物件を売却するのであれば再建築不可物件を得意としている買取業者に相談しましょう。再建築不可物件を専門的に取引しているため、断られたり売れなかったりというリスクは低いです。物件の活用ノウハウに関しても豊富なので一般的な不動産会社よりも高値で売れる可能性があります。また、業者を選ぶ際には契約不適合責任が免責となっている会社を選びましょう。売却後のトラブルに巻き込まれるリスクを大きく軽減することができます。
トラブル不動産売却センターでは再建築不可物件をはじめとしたトラブル不動産を専門的に取り扱っています。神奈川県内の買取実績No.1。数々の再建築不可物件を取り扱ってきて、活用ノウハウや販売網が豊富なので、他者では断られるような物件であっても好条件での買取りが可能です。もちろん契約不適合責任は免責なので、そのまま物件をお譲りください。建て替えも増築もできない再建築不可物件にお悩みなら、ぜひ私たちにご相談ください。
なお、再建築不可物件の売却のポイントについては「再建築不可物件の相場とは?不動産会社に騙されない虎の子秘伝を公開」でご紹介しています。私たちだからこそ知る業界の裏話も交えながら、好条件で売却できる最適な方法をご説明していますので、ご興味がありましたらぜひお読みください。